 それぞれの地域には様々な生きものが棲息している。そうしてそこで暮す人々の生活や精神世界に深く関わっている。生きもの達は生活に役立つとても身近な存在だったり、深い森に隠れ住む神秘的な存在だったりして、人間達に対し千差万別な関わり方をしてきた。アジアの国々ではそういう実生活のリアリティーに、神話や宗教に登場してくる生きもの達のイメージが重なり、とても豊かで親密な「生きもの」像が育まれてきた。
それぞれの地域には様々な生きものが棲息している。そうしてそこで暮す人々の生活や精神世界に深く関わっている。生きもの達は生活に役立つとても身近な存在だったり、深い森に隠れ住む神秘的な存在だったりして、人間達に対し千差万別な関わり方をしてきた。アジアの国々ではそういう実生活のリアリティーに、神話や宗教に登場してくる生きもの達のイメージが重なり、とても豊かで親密な「生きもの」像が育まれてきた。<テーマ・アジアの生物達>
 それぞれの地域には様々な生きものが棲息している。そうしてそこで暮す人々の生活や精神世界に深く関わっている。生きもの達は生活に役立つとても身近な存在だったり、深い森に隠れ住む神秘的な存在だったりして、人間達に対し千差万別な関わり方をしてきた。アジアの国々ではそういう実生活のリアリティーに、神話や宗教に登場してくる生きもの達のイメージが重なり、とても豊かで親密な「生きもの」像が育まれてきた。
それぞれの地域には様々な生きものが棲息している。そうしてそこで暮す人々の生活や精神世界に深く関わっている。生きもの達は生活に役立つとても身近な存在だったり、深い森に隠れ住む神秘的な存在だったりして、人間達に対し千差万別な関わり方をしてきた。アジアの国々ではそういう実生活のリアリティーに、神話や宗教に登場してくる生きもの達のイメージが重なり、とても豊かで親密な「生きもの」像が育まれてきた。
生きもの達はしばしば特定の部族や家系のトーテム、守護神ともなり、神々の化身、使い、乗り物、贈り物ともされてきた。そうしてそれは生活を支える重要な食料であり、労働力でもあり、戦争のための戦力、富や権力の象徴ともなったし、愛贋物にもなってきた。
アジアでは生活のあちらこちらで犬、猫、猿、鳥、豚、牛、馬、、、などがかってきままに行き来しているように、彼らの造り出すものにも、それら生きもの達が頻繁に登場してくる。それらは単なるモチーフや装飾として登場してくるに留まらない。元来人は、生きものについて考えるだけではなく、生きものによって、世界や人間という存在を思考てきたに違いないのだ。
1、神域 − 神獣、神の化身、神の乗り物、神の使い
2、野性 − 危険な猛獣、獲物、神からの贈り物、意味不確定な全ての生物
3、家畜 − 食料、労働力(農耕、運搬、狩猟等)、愛贋物、乗り物、武器、、、
人間にとっての生物は、<神域−野性−家畜>という流れをその本質に持っている。いわば山、森、海など奥深い自然領域を徘徊する「野性」状態は、神の領域と人間の生活空間の中間領域と位置付けられ、そのどちらにもつながっていると考えられる。人間の生活空間に必要な基礎的な多くのもの(命、食料、災い、幸運、水、土地、、)がその外側に広がる野性的自然、さらにその背景になる神々の領域に由来しているとされ、しばしば野生生物達はその「外部的領域」のシンボルとして重要な仲介者的役割り担わされることになる。
ユダヤ・キリスト教の場合、野生動物と家畜は厳正に別けられており、本来的に異なる存在と位置づけられる。家畜ははじめから家畜であり人間のために働き、食われるために存在している。それゆえキリスト教では基本的に「野性動物−家畜」間の移動の自由はほとんど無い。一方アジア的な世界観では牛や象、馬という家畜化されている動物達がしばしば神聖視され、人間を越えた力を秘めているとされることが多い。そこでは家畜化という状態を本来的なものとするよりも、ある一時的状態とする感覚がある。生きもの達のいくつかは、たとえ家畜化されようとも、人間の僕となりさがろうとも、どこまでも元来の生物的野性を失わず、「生命」現象という人智を越えた一点で、神々の領域、そうして人間自身に対してどこかでつながりを保ちつづけることができる。
それゆえに野生動物を生活空間に確保するという行為は、時に神からの贈り物(めぐみ)を受け取る行為であり、あるいは神聖な野性的力を味方とし、確保し、自らのものとする権威のシンボルともなる。逆に一度確保した生物を再び逃がすという行為は、もとの状態に帰すという意義深い、慈悲的な行為となりうる。捕まえた小鳥を逃がして功徳を積む行為はアジアで広く行われている。アイヌの「イオマンテ」は「それを送る」という意味だそうだが、神からの贈り物としての獲物を有り難くいただき、その魂を儀式的に「もと」の領域へ丁寧に帰すわけで(ここでは逃がすのではなく殺すわけだが)同じ原理が生きているのが解る。肉と霊を通じ合わせながら「もらったらかえす」という交換による象徴的なバランスがつくられその中に動物と人間の交流がある。
<造形の構造と生きものモチーフの関係>
それぞれの生きもの達には様々な象徴性が付与されている。それは各々の特徴ある身体構造に由来していたり、その生態的特徴からきていたり、あるいは神話的エピソードに依拠するものだったりするわけである。「生活用品」に由来する種の人芸品の場合、その機能的な働き、あるいはそこからくる造形構造、象徴的意味合いと、そのような生きもの達の身体構造、生態、そうして象徴性をアナロジックにドッキングさせて行くことが多い。
 |
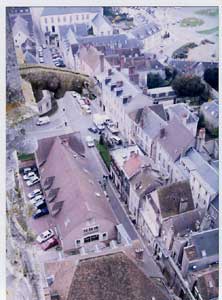 |
| 象徴的な文様が付された縄文式土器 | 怪異な動物の姿をしたシャルトル大聖堂の排水溝 |
 |
 |
| コブラ(ナーガ)の形態を生かした寺院の塀(ミャンマー) | 蓮の花を台座にしたロウソク立て(ミャンマー) |
 |
 |
| 象の急須、魚の入れ物、箸置き、亀の入れ物(タイ) | 魚の形を生かした皿(タイ、イタリア) |
例えば壺はしばしばその空洞を宿した膨らみのある形状から女性の子宮に例えられ、死者の遺骸が葬られたりした。器の台にしばしば足が取り付けられると象や馬、あるいは亀などの生き物に例えられ、顔が取り付けられたりする。イス、テーブル、様々な台などでもしばしば四つ足の重い荷物を背にのせることのできうる生物(象、馬、牛、亀、、)のイメージが重ねられる。特に供物を入れたり、墓に捧げる特別な容器では、神々の世界を行き来する使者、乗り物としての聖獣的イメージと重ねられる。注ぎ口の付いた水指し等ではその口の部分が象や魚の口とだぶらされることもある。蛇や龍はその流動的形状からあらゆるものの装飾、取っ手、縁取りとなって登場する。それはそうしたスペースを守護する魔よけとして機能する。神や魔物の尻尾、髪の毛(メデユーサの髪)、首飾りが蛇(シバ神)だったりするのもその形状のせいであろう。建物は元来このような象徴の宝庫である。柱は上昇する植物に例えられたり(ギリシャ神殿やそこに発する全ての西洋建築)、空に突き出た先端部は植物の新芽、窓は花、複雑に交差する装飾模様はしばしば草花の蔦にたとえられたレリーフとなっている。排水溝の先端部には様々な生きものや怪物の顔が施されその口から水が放出される。建物の重圧を支える礎石に亀や人間、過去に信じられた魔物達の姿が登場してきたり、仏塔ではその基台に象(39匹)が選ばれる(世界を支える仏教説話)こともある。それらは世界を支えるもの、あるいは礎としての時に犠牲的存在に由来すると言えよう。ラ−オ文化圏の寺の基本的モデルは卵やひな鳥を守る親鳥の姿に由来していると言われ、暖かみのある安定性にとんだ優雅な雰囲気をたたえている。犬はよく吠えるので番犬として、魔よけの彫刻として建物の入り口付近に狛犬等として多く登場してくる。蓮華の花は仏教では理念的な世界像のメタファーとなっている。仏陀が座るのも蓮華の花の上である。仏塔の先端部が蓮のつぼみにたとえられることもある。アジアで魚のモチーフは皿によく登場してくる。水に満たされた器の中を気持ちよく泳ぐ様に、あるいは魚と皿の平たい流線形の形状がシンクロするようにデザインされる。
このような実用品と動植物との造形的、象徴的融合は、単なる装飾や、洒落、遊びという意味合いを越えて、本質的でドラマチックで必然性に満ちたすばらしいものである。このような異界(生物、宇宙と人間)との交流、異種間の有機的結合は、モダニズムや民芸運動が提示する矮小なリアリティーから完全に無視されてしまっている。
<神の乗り物としての生もの達>
 |
 |
| 牛(ナンディ)にまたがるシバ神(インド) | 魚に乗る子供の張り子(沖縄) |
生もの達はしばしば「神の使い」とされたり、「神の乗り物」とされる。時には神や精霊の「化身」と位置づけられることもある。乗り物とされる動物で多いのは、やはり普段人間をのせることが多い四つ足の動物達である。だからといって「神の乗り物」を普段の生活体験から派生したと考えるだけではすまない。「乗り物」というのはおそらく一つの例えであって、もともとの動物達の存在自体の両犠牲に端を発していると考えたい。まず「乗り物」以前に、動物達の「背」が神々の憑依する「御座」として、「場」として機能していると考えられる。そうしてそれは神自身でなくともよく、「神意」や「おくりもの」が動物に乗せられ人間界にもたらされたり(動物の肉そのものが贈り物と位置付けられたりする)、逆に人間側の願いや「おくりもの(供物)」が動物に乗せられ、神域へ運ばれたり(この場合はいわゆる「生け贄」だったり神社への「絵馬」奉納だったりする)することが多いように思う。ようするに動物達は乗り物である前に神域と人間界をつなぐ「媒体」なのである。媒体という性質は、人間から見て「自然」と「人間」の間に動物達の存在が位置付けられていることから必然的にくるイメージである。そのため生きもの達は自然や神の「使い」、「乗り物」、「化身」、「よりしろ」としてイメージされる。
馬というのは神の乗り物として日本人にもなじみが深い。元来「生け贄」、「奉納馬」から「絵馬」となり今日でもまだそのなごりがある。本来日本列島には馬が生息していなかったらしく、とても貴重であったと想像される。その能力も優れていて陸上の乗り物では当時もっともスピードがった。戦闘でもそれが重要な戦力となり、指揮官や位の高い人間の乗り物でもあった。西洋では高貴な者が乗る「騎馬像」が一つの伝統的シンボリズムになっており、幸いコンスタンチ大帝の像と間違えられたおかげで、危うくキリスト教の偶像破壊活動から難をのがれることができた古代ローマ皇帝マルクス・アウレリウスの騎馬像をはじめ、多くの記念碑的モニュメントが作られてきた。ルネッサンス期にも、ドナテロやヴェロッキオやレオナルドなどの巨匠がその腕を競ってきた最も高貴な記念碑的ジャンルであった。近代以降も繰り返され、特にマリノ・マリーニの連作は有名である。「騎馬像」のイメージは馬の野性的力を引き出し、制御し、上手にコントロールする、自然と人間が絶妙に結合して生まれる「文明」そのものの理想的統合の象徴と位置付けられる。それゆえ帝国や共和国、軍団の統率者は、自身の姿を騎馬像として永遠にモニュメント化することを強く望んできた。
 |
 |
| ローマ皇帝マルクス・アウレリウス騎馬像 | 日本の絵馬 |
世界各地の神々は各々の特定の持ち物や衣装を持っているように、ある特定の生き物と強い関係を持っていることが多い。 乗り物とされるのはその一貫であろう。ヒンズー教では各々の神々が対抗するように様々な特定の動物が乗り物になっていて面白い。シバ神はナンディ(牛)、インドラ神は象、ヴィシュヌ・クリシュナ神はガルーダ、シバ神の子・スカンダは孔雀、シバ神のシャクティ・ドウルーガはトラ、ヴラフマ−神は白い鳥やワシ、ヴィシュヌ神の化身カルキンは白馬、、。また仏教ではナーガ神がその身をていして仏陀を嵐から守る話があり、コブラ(ナーガ神)と仏陀が組み合わされる像が多い。これは乗り物というよりも仏陀を守る強力な玉座の様にも見える。コブラの平らな頭が傘となり、とぐろが螺旋上にせりあがり、蓮華の花に座る仏陀のタイプとまた違って、力強くエキゾチックな造形となっている。この組み合わせは日本ではほとんど見られないが蛇はなんらかの守護神となることが多い。また動物の背中に乗るのではなくて、神や貴人、軍人が乗る山車を引く姿で造形化されることもある。インドでは象が山車をひいている姿が石によってそのまま神殿になっているものもある。
さて乗り物というにははばかられるが、この世界そのもの、宇宙そのものを乗せているというイメージが亀や象に付与されることがある。例えばヴィシュヌ神の化身ク−ルマという亀はマンダラ山を背にのせることになっているし、中国神話では四本の天を支える柱の一本が耐えられなくなった時、亀の足を切り取って代用された。バリ島の神話でも八層の亀とそのまわりを巻いたナーガ(蛇)がセットになって世界を表している。古代中国の四方を守る聖獣の一つ玄武も同様の姿をしている。浮かんでいる島の木を切ってたき火をしていたらその島自体が亀で、熱くなった亀が水中に潜ってしまい、上陸していた人間達が溺れ死ぬという神話もある。仏教では象が世界を支えているというイメージがあり、仏塔の土台に象が用いられることが多い。亀や象はすばやく移動するというよりも、ものすごい重量を下で支えてくれているというようなニュアンスである。そうなってくると大建築物を土台で支える様々な生き物、怪物達ともつながっていく。逆にこの世界をあらわす輪廻の車輪の上に乗って、踊り続けるというナタラージャ(シバ神)のようなイメージもある。
<暦と動物>
日本の十二支は古く中国から十干と一緒に伝来したらしい。セットになって年月日を表すのに使われてきた。なぜ子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥という動物が当てはめられてきたかははっきりしない。虎や羊は日本にいないし、辰は中国の想像上の聖獣である。ちなみに一日の時間を表す午前・正午・午後もここから来ていて、午とは馬のことで馬を基軸にして時を表現しているのが解る。さらに「丑三つ時」、「子の刻」などと一日を細かくきざんでもいく。
中国と言えば東西南北を各々青龍・白虎・朱雀・玄武という聖獣に守護させるという思想がある。暦ではないが方角も動物(聖獣)によって表現されることになる。
ミャンマーでは各曜日(週8日制、水曜日が午前午後に別れる)ごとに方角、星、そして動物(牙のないゾウ・モグラ・鳥・ネズミ・ナ−ガ・牙のあるゾウ・ライオン・虎)が配されセットになっている。ここでは何曜日に生まれたかが重要視され、曜日を象徴する動物の土産物も多い。
古代ギリシャ人も夜空の星達を星座としてとらえ、様々なイメージをその星達のならびに応じて発想し当てはめた。その中には羊、山羊、牡牛、サソリ、蟹、など生き物も多く含まれている。これは天体の動き、すなわち暦に通じ、地上の人間の生に大きく影響すると考えられてきた。
このように様々な地域で動物達が暦、時刻、方角を表し、それらを象徴的に表現してきたのが解る。一種類の動物が問題にされるのではなく十数種類がワンセットに体系化され、各々が全体の中であるウエイトを示していく。その体系化される生物群はそのままその地域の風土が反映されていて興味深い。人類は動物とともに生き、動物を通して宇宙に関わり、動物によってこの世界を思考してきたのである。それは単なる記号や数字の表記と違って、各々の風土に根ざした、リアルでファンタジックな体験様式、文化そのものだったと言える。