黒目玉の気韻
<はじめ>
 表情・目玉というのはもともと造形表現の重要な要素の一つである。仏像や神像などでもその表情を眺めることは人々の欲求でありとても意義深い体験を喚起するものである。このような体験と「美術」の鑑賞でえられる体験が、時としてかけ離れたもののように考えられるようになるのはそんなに古いことではないと思う。表情・目玉はその造形の性質を決定的に左右するものであるだけでなく、それが生まれた時代、作者の人格、気持ち、世界観など諸々が如実に現れてしまう。仏像の表情も鎌倉室町を過ぎると悪くなると言われるように、いい顔悪い顔というのが長い歴史を通して確かにある。例えば東北地方の「こけし」はほとんど表情のみの木地人形であるが、その表情の微妙なかき分けを各師弟筋ごとに受け継ぎ守ってきていて、それら様々な顔、ニュアンスを味わうのがコレクター醍醐味なのだが、戦後のこけしに良いものは少ないといわれる。
表情・目玉というのはもともと造形表現の重要な要素の一つである。仏像や神像などでもその表情を眺めることは人々の欲求でありとても意義深い体験を喚起するものである。このような体験と「美術」の鑑賞でえられる体験が、時としてかけ離れたもののように考えられるようになるのはそんなに古いことではないと思う。表情・目玉はその造形の性質を決定的に左右するものであるだけでなく、それが生まれた時代、作者の人格、気持ち、世界観など諸々が如実に現れてしまう。仏像の表情も鎌倉室町を過ぎると悪くなると言われるように、いい顔悪い顔というのが長い歴史を通して確かにある。例えば東北地方の「こけし」はほとんど表情のみの木地人形であるが、その表情の微妙なかき分けを各師弟筋ごとに受け継ぎ守ってきていて、それら様々な顔、ニュアンスを味わうのがコレクター醍醐味なのだが、戦後のこけしに良いものは少ないといわれる。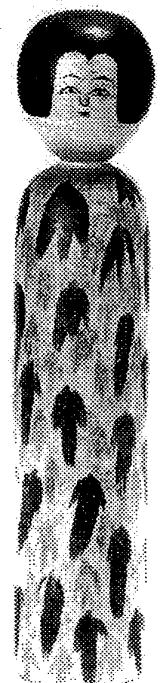 こけしに限らずあらゆる局面で、総じて現代人はどうも「良い」顔が書けなくなってきている傾向にあり、理由としてはいろいろ取りざたされるが、間接的には社会が近代化したこと、直接的には、誤った西洋史前主義的描写の学習、マンガアニメ的表現の影響などがあげられる。このような諸々の表情・目玉の善し悪しはどのような点で決まってくるのだろうか。また近現代の絵、もしくはマンガアニメのそれと比べどのような違いがあるのだろうか。表情の中でもとりわけ重要な「目玉」に話をしぼってそれらのことを少し考えてみたいと思う。
こけしに限らずあらゆる局面で、総じて現代人はどうも「良い」顔が書けなくなってきている傾向にあり、理由としてはいろいろ取りざたされるが、間接的には社会が近代化したこと、直接的には、誤った西洋史前主義的描写の学習、マンガアニメ的表現の影響などがあげられる。このような諸々の表情・目玉の善し悪しはどのような点で決まってくるのだろうか。また近現代の絵、もしくはマンガアニメのそれと比べどのような違いがあるのだろうか。表情の中でもとりわけ重要な「目玉」に話をしぼってそれらのことを少し考えてみたいと思う。
私の場合、子供の頃からマンガを描くにしても絵を描くにしても、目玉をどう描くかは常に最大の関心事で、スタイルの数ほど目玉の種類があり、新しい眼の描き方は新しい絵の描き方に等しかった。「美術」をやるようになってもしばらくは目玉にこだわっていた。レンブラントやゴッホがよくて、ルーベンスやプッサンがダメだと思ったのも結局は目玉によってだった。それがだんだん「造形性」とか「セザンヌ」とか「現代美術」とかいっているうちにどこかに吹き飛んで目玉を描くことができなくなってしまった。当時日本で人物を描いていた画家は横尾忠則ひとりぐらいで、自分の作品づくりがいつの間にか目玉と無縁なものになっていた。目玉への執着心というか探究心はその後潜在化されドロドロと曲がりくねり沈澱されたまま現在にいたっている。そうこうしているうちに昨今のコンテンポラリーアートでは人というか、顔というか目玉というかそういう描写が溢れだしてきた。こういう極端な変化はどう考えてもちょっとおかしい。目玉を描かなかった以前がおかしいのか、目玉が解禁された今がおかしいのかというよりも、そういう極端な変化が目立った対立や議論の無いままやり過ごされているのが滑稽にうつる。そしてそのような今日氾濫する目玉達は、自分が意識化でこだわり続けている目玉の在り方と比較しつつ観察するにおよび多くの疑問を禁じえない。
<動勢>
東洋の画論に「気韻生動」というのがある。絵というのは元来静止したものであるから、その静止の中にいかに生命的な動勢を表しむるかということに常に腐心して来た。たしかその極意の一つに「動き」の一歩手前のギリギリのポイントを重視する、描写するというようなものがあったと記憶する。例えば人が走っている動きを表現する場合、激しく走り続ける最中の描写をするのではなく、いままさに走り出そうとする瞬間、身体を動かす一歩手前を鋭く描写しなければならない。派手に手足をばたつかせている最中の描写をしても、そのとおり走っている姿の止まった絵でしかなく、絵としての動勢が生まれることとは別問題なのである。未来派の画家バッラが描いた犬の散歩の絵は好例で、いくら足の動きを丹念に描写しても、なぜか逆にその動き、その絵そのものを一時的で限定されたものにしてしまう。時間の動きを描けば描くほど絵の中に流れる時間は限定され、その瞬間に規定されてしまう。
動き出す一歩手前を描くというのは、見る側に、今にもその対象が動きだしそうな気配、動勢を想起させることにつながる。そうしてその動勢の気配は静止した作品とともに半永久的に続いていくものでもある。またその動勢は寸止めされているので、その動きが何処へどういうふうに具体化されるかという限定を免れ、したがってその絵自体も限定されない広がりを獲得しうる。動きというのは常に具体的な限定された時間の中で展開されるものであり、一方静止とは永遠を暗示するものだ。この両極を同時に表現してしまう知恵は、瞬間と永遠、動きと静止、現実と理念を結合するものであり、東洋のみならず良質の造形作品の必要条件の一つと言える。
<永遠とリアル>
ところでこのような知恵を西洋では古代は別としてジョット以前には持ち合わせていなかったとしか言い様がない。中世のキリスト教的造形表現では決められた規範に図式的、幾何学的に登場モティーフが当てはめられ組み合わされる。神の国の永遠の規範は常に幾何学的で静止的だった。 その場合の登場人物の身ぶりは形式的、図式的で、一種の記号のようなところがあり、自然な身体の動き、動勢からは程遠いものが大半であったし、そこからはみだすものは稚拙なものばかりだった。それがチマブエ、ジョット以来生きた人間、現実の動き、表情というものが導入されるようになっていく。静止的な規範は後退し、画面構造として絵を背後から支えていくようになり、描かれる人物達はよりドラマチックに、よりリアルに描きわけられ、見る側に臨場感を誘う努力がほどこされはじめる。
その場合の登場人物の身ぶりは形式的、図式的で、一種の記号のようなところがあり、自然な身体の動き、動勢からは程遠いものが大半であったし、そこからはみだすものは稚拙なものばかりだった。それがチマブエ、ジョット以来生きた人間、現実の動き、表情というものが導入されるようになっていく。静止的な規範は後退し、画面構造として絵を背後から支えていくようになり、描かれる人物達はよりドラマチックに、よりリアルに描きわけられ、見る側に臨場感を誘う努力がほどこされはじめる。
ここで「眼」はその表情とともに最大の表現効果を発揮し、あっちを見たりこっちを見たり、悲嘆にくれたり、怒りを燃やしたり様々に描きわけられていく。この革新的動向をキリスト教美術の世俗化、通俗化、演劇化ととらえることも、現実世界に足をおいた活力ある統合ともどちらにも言うことができる。
このような静止と動き、永遠とリアルさは、宿命的に静止した造形表現の本質的問題であり続けた。そうして一般論として言えばそのバランスが、永遠性により振れるならば、形式的で近寄りがたい生硬な表現になり、リアルさに振れるならば、世俗的、通俗的な一過性のモノに落ちていく。これは壁面全体、大画面全体に対してと同様に、ひとりの人物、一つの表情、一つの目玉の描写へ集約されていく問題でもある。
とくにそれは単体の偶像表現、イコンとしての表現において顕著であり、その本質が行き着くところでありかつその原点でもあると考えられる。偶像表現はその存在条件として、まず超越的な聖性と同時に、人々を引き付けるリアリティーの両面が常に必要とされる。そうしてその両面がその表情に最もよく集約されると言える。それにくらべれば、壁画や絵画の群像表現の中の一人物の比重は軽く、多くの場合、全体表現の一部として機能し、引き立て役だったりするので、わざわざ通俗的に表現されたり、あるいはその逆だったりするので、群像のなかからひとりの人物だけを取り出してその絵全体についてうんぬん言うことはできない。
<偶像・正面性・目玉>
 目玉や表情というのは実際のところよく動く。感情の動き、興味の変化に応じてそのニュアンスが刻々と変わっていく。その動きを静止した造形表現において志向する場合、先に述べた身体の動きにおける「気韻生動」と同様の問題が現れてくることがわかる。目玉や表情にもその気韻生動が生かされなければならず、したがって動き(変化)の一歩手前で寸止めされる必要がある。いくら怒りによって顔を崩した表情を造ったとしてもそれはそれだけのモノでしかなく、派手なわりに長続きするものではない。本当の怒り、恐さはやはり怒りの爆発の手前、爆発を予見させつつ、「ため」を持った「憤怒」の表情であり、目玉である。
目玉や表情というのは実際のところよく動く。感情の動き、興味の変化に応じてそのニュアンスが刻々と変わっていく。その動きを静止した造形表現において志向する場合、先に述べた身体の動きにおける「気韻生動」と同様の問題が現れてくることがわかる。目玉や表情にもその気韻生動が生かされなければならず、したがって動き(変化)の一歩手前で寸止めされる必要がある。いくら怒りによって顔を崩した表情を造ったとしてもそれはそれだけのモノでしかなく、派手なわりに長続きするものではない。本当の怒り、恐さはやはり怒りの爆発の手前、爆発を予見させつつ、「ため」を持った「憤怒」の表情であり、目玉である。
目玉-眼球は基本的に白目と黒目に別れるが、この黒目が上下左右(東西南北)自由に動き感情、興味関心の方向を暗示する。先の「寸止め」の話であきらかなように、その目玉自体が正面性の単体-偶像の目玉として、超越性とリアルさを同時に表出しようとする限りにおいて、黒目は基本的に白目の中心にこなくてはならないことになる。これは単体偶像の眼球の基本である。黒目が動き過ぎると、その興味関心が、ある方向に限定されすぎて、目玉の持ち主の感情、意志が限定的に表れすぎてしまう。そのような感情、意志、興味関心の多分に現れたまなざしは、言ってみれば実際の人間的まなざしであり、見る側にとって感情移入しやすく共感されやすい半面、超越性、永遠性を損ないやすい。一方基本どおり黒目が中心にあると、その前にいる観者は、感情の機微すら不明の静止したオブジェのような眼球に、まっすぐ凝視され続けその力にうちひしがれる。その目玉は我々の視線とちがってまったく微動だにせず、何もかも見通してしまうと思わせることすら可能となる。黒目の移動は、興味関心の方向性は表すが、その顔面、目玉の持つ強度、意志の力自体は逆に分散させてしまうことになる。
このような黒目を白目の中心に置く基本もあまりにも図式的にパターンかされるなら、死んだ魚の目玉のように、精気を失い空虚な距離感ばかり感じさせてしまうことになる。白目に黒目を入れるのは、ズレすぎず、真ん中すぎず、常に「画竜点晴」でなされなければならず、表現全体に「気」が宿るかどうかを左右する重要な一点のなのである。
キッチュな品々や、漫画的描写、キャラクターの場合、その必要性から、手っ取り早く感情、気持ち、意味を表し共感されるために、大袈裟に表情をつくりかつ目玉もそれにともない大きく動かす場合が多い。そのため例えば犬や熊、架空の化け物までが大変人間的な感情を通わせてしまうこともあり、ある意味において通俗的、陳腐な表現になることが多い。今日氾濫するマンガアニメ的な描写の流用、無自覚な影響は、そういう意味でだいたいの場合陳腐な結果に終っている。マンガアニメは時間的表現形式であり、静止した絵画や彫刻にそのまま流用されるなら必然的にマンガアニメに遠くおよばない一枚の陳腐なイラスト、もしくは工芸化されたイラストに帰結する。それらはマンガアニメ的表現だから、平板だから、ダメなのではなく、時間表現で展開されるべき過剰な表情をそのままタブローに用いることではっきりするその陳腐さがダメなのである。その陳腐さ、キッチュさはその作品がいかに重大な文化戦略を意図していると言えどもかわりはなく、古今東西普遍のものである。これまでもマンガアニメ的表現が近現代の子供達、大人達の絵、あらゆるものづくりを犯していったように、いよいよ造形芸術までもその根底から犯しはじめていると捉えることもできるし、すでに犯されていたことに自覚的に開き直ったとも言えよう。
<いろいろの目玉>
このような黒目を白目の中心に置く「基本形」から様々なバリエーションが想定される。今日ではありふれた単体の肖像画も、後述するようにその根底ではこの単体偶像表現に顕著な「基本形」を下敷きにしてることがわかる。ここではそのような様々な具体例をあくまで「基本形」の変形バリエーションとしてとらえながら記述してみようと思う。一見無造作に様々な目玉が造り出されているようで、実は「基本形」のエッセンスを異なる状況、次元で各々に守り続けているのがわかる。





例2では目玉の中の黒目がなくて、白目が光を発するかたまりに進化しており、人間的な意味での感情関心をあらわす視線とは違った超越的な眼となっている。この場合粘土性の野暮ったい顔面表現が憎々しいほどの現実感をともないながら超越的な目玉と対比されている。例3では逆に黒目だけで、さながら穴のようでもある。たしか岡本太郎が、目玉とは宇宙にあけられた穴だというようなことを言っていたと記憶するが、まさに中に何がつまっているのか、どんな感情、心があるのかはかりしれない謎めいた感じである。その穴は見えない無限な領域と通じているにちがいない。例4は目玉自体、顔自体が無い。そこには表情や気持ちが謎で、視線そのものが無いのでただ見られる一方かと言うと意外にそうでもなく、目玉で見える事柄とは別のレベルに訴えかけてくるもう一つの見えない視線を発しているように思う。

ところで目玉の持ち主が何らかの理由で、見る側の人間と平行に向かい合う位置関係にない場合では、さらに複雑な目の動きが生まれてくる。例5は黒目がやや白目の下の方に移動するタイプであるが、その目玉の持ち主が人間サイズを越えて大きなものだったり、高い位置にいたりする時に多い。大仏や天上から見下ろす神の像などの目玉がそうで、上から見下す威圧感をともなう目玉である。例6は逆で、黒目が白目の上の方にくるもので、下から上を見上げるまなざしである。一種恨めしさのただようものであり、顔の角度を下に向けつつ前方を鋭く睨むような威圧的な憤怒の表情でよく見かける目玉である。ちなみに奈良美智の多くの子供の絵はこのタイプの目玉をしており、子供が下方から我々大人を恨めしく見上げる形になっている。逆に言えば我々見る側が上から子供を見下す視線になっている。さらに黒目が見る側の視線に向けられるのではなく、よりいっそう上方に向けられる例7では、絵の主題が目玉の放つ視線の向かう方向、つまり画面のさらに上に放たれていく。 それは暗に画中の聖職者が夢中で思いを巡らす神のことがら、形而上の世界へ向けられている。いわば神的偶像が視線を見る側に浴びせるのに対し、神との仲介者である聖職者の視線は文字どおり仲介となることで見る側の視線を上方へ誘う(同時にただ一方的に見られる対象物となった聖職の無防備な姿形が、生々しくそこに浮上してくるところがこの絵の肖像画としての面白いところでもある)。
それは暗に画中の聖職者が夢中で思いを巡らす神のことがら、形而上の世界へ向けられている。いわば神的偶像が視線を見る側に浴びせるのに対し、神との仲介者である聖職者の視線は文字どおり仲介となることで見る側の視線を上方へ誘う(同時にただ一方的に見られる対象物となった聖職の無防備な姿形が、生々しくそこに浮上してくるところがこの絵の肖像画としての面白いところでもある)。
例8ではもはや顔も視線も観者に無関係な方向に向けられ、見る/見られるという単体偶像表現に顕著だった主体同士の相互関係はなくなり、一方的に見られる対象となっている。いわゆる自然主義的西洋絵画に登場する多くの人物がこのようなただ見られるものとして全体のための一部分として機能されるように配置されるタイプのものである。このようなただ「見られる人物」は何らかの場面、出来事、歴史的記述、歴史的人物としてのポ-トレイトとして頻繁にもちいられ、「基本形」とは最も遠いところにあると言える。
 例9のケースはルネッサンス以後の西洋的肖像画に最も多いパターンで、言ってみれば古典的目玉タイプと言えるものであり、その代表はモナリザであろう。顔は画面に対してわずかに斜をむいていて、黒目のみが画面正面に立つベき見る側に向けられている。ポーズとしては大変自然で現実的なものである。それでいながらそのまなざしは見る側に真直ぐ向けられている。いわばイコンとしての正面性を、その超越性を失わずに、より自然で現実的なたたずまいとしてずらしながら合成しなおしたようなところがある。このタイプは中世的伝統と古典的自然主義が合体されたものとして考えられるべきであろう。偶像としてのイコンがリアルな女性としての一瞬の注視をこちらに向ける。それは一瞬の微妙なものでありながらなぜか永遠性を強く感じさせる表現になっている。現代の感覚から見ればそれはたんなる肖像画であり、そういう形式でありながら、何らかの超越性をともなうイコンを彷佛とさせることができている希有な作品になっている。モナリザの目玉はその顔面を正面から見たとすれば例9のようになっているはずで、まったく雰囲気をかえてしまうはずで、角度を変えて見れば通俗的な表情としてうつるはずのモノである。「基本型」から言えばモナリザの黒目自体は移動のしすぎであり、事実他の画家によって模写された偽物ではそれがネックとなり通俗性に落ちてしまい、誰ひとりとして真似ができない。
例9のケースはルネッサンス以後の西洋的肖像画に最も多いパターンで、言ってみれば古典的目玉タイプと言えるものであり、その代表はモナリザであろう。顔は画面に対してわずかに斜をむいていて、黒目のみが画面正面に立つベき見る側に向けられている。ポーズとしては大変自然で現実的なものである。それでいながらそのまなざしは見る側に真直ぐ向けられている。いわばイコンとしての正面性を、その超越性を失わずに、より自然で現実的なたたずまいとしてずらしながら合成しなおしたようなところがある。このタイプは中世的伝統と古典的自然主義が合体されたものとして考えられるべきであろう。偶像としてのイコンがリアルな女性としての一瞬の注視をこちらに向ける。それは一瞬の微妙なものでありながらなぜか永遠性を強く感じさせる表現になっている。現代の感覚から見ればそれはたんなる肖像画であり、そういう形式でありながら、何らかの超越性をともなうイコンを彷佛とさせることができている希有な作品になっている。モナリザの目玉はその顔面を正面から見たとすれば例9のようになっているはずで、まったく雰囲気をかえてしまうはずで、角度を変えて見れば通俗的な表情としてうつるはずのモノである。「基本型」から言えばモナリザの黒目自体は移動のしすぎであり、事実他の画家によって模写された偽物ではそれがネックとなり通俗性に落ちてしまい、誰ひとりとして真似ができない。 このような構図、このような目玉の肖像画はレオナルド以後も肖像画の常套パターンとして、現在にいたるまで数多く描かれて来ているが、「立派な肖像画」、「良質の絵画」の域を出るものではない。そこでは「単体偶像表現」が持っていたものと同質の超越性、深遠性を「肖像画」というか「絵画芸術」に持ち込むことに失敗している、と言うよりもそういう次元そのものがその後の「美術」から忘却されてしまったのである。深遠な世界観を担ってきた中世的な、さらに広く言えば偶像表現的な顔・目玉-気韻生動のエッセンスは、レオナルドを一つの頂点として、あるいは分岐点として「美術」と袂をわけ、宗教や呪術というものに押し込められてしまったと言えるだろう。
このような構図、このような目玉の肖像画はレオナルド以後も肖像画の常套パターンとして、現在にいたるまで数多く描かれて来ているが、「立派な肖像画」、「良質の絵画」の域を出るものではない。そこでは「単体偶像表現」が持っていたものと同質の超越性、深遠性を「肖像画」というか「絵画芸術」に持ち込むことに失敗している、と言うよりもそういう次元そのものがその後の「美術」から忘却されてしまったのである。深遠な世界観を担ってきた中世的な、さらに広く言えば偶像表現的な顔・目玉-気韻生動のエッセンスは、レオナルドを一つの頂点として、あるいは分岐点として「美術」と袂をわけ、宗教や呪術というものに押し込められてしまったと言えるだろう。
雑誌『インファンス』№10・2003年掲載
 表情・目玉というのはもともと造形表現の重要な要素の一つである。仏像や神像などでもその表情を眺めることは人々の欲求でありとても意義深い体験を喚起するものである。このような体験と「美術」の鑑賞でえられる体験が、時としてかけ離れたもののように考えられるようになるのはそんなに古いことではないと思う。表情・目玉はその造形の性質を決定的に左右するものであるだけでなく、それが生まれた時代、作者の人格、気持ち、世界観など諸々が如実に現れてしまう。仏像の表情も鎌倉室町を過ぎると悪くなると言われるように、いい顔悪い顔というのが長い歴史を通して確かにある。例えば東北地方の「こけし」はほとんど表情のみの木地人形であるが、その表情の微妙なかき分けを各師弟筋ごとに受け継ぎ守ってきていて、それら様々な顔、ニュアンスを味わうのがコレクター醍醐味なのだが、戦後のこけしに良いものは少ないといわれる。
表情・目玉というのはもともと造形表現の重要な要素の一つである。仏像や神像などでもその表情を眺めることは人々の欲求でありとても意義深い体験を喚起するものである。このような体験と「美術」の鑑賞でえられる体験が、時としてかけ離れたもののように考えられるようになるのはそんなに古いことではないと思う。表情・目玉はその造形の性質を決定的に左右するものであるだけでなく、それが生まれた時代、作者の人格、気持ち、世界観など諸々が如実に現れてしまう。仏像の表情も鎌倉室町を過ぎると悪くなると言われるように、いい顔悪い顔というのが長い歴史を通して確かにある。例えば東北地方の「こけし」はほとんど表情のみの木地人形であるが、その表情の微妙なかき分けを各師弟筋ごとに受け継ぎ守ってきていて、それら様々な顔、ニュアンスを味わうのがコレクター醍醐味なのだが、戦後のこけしに良いものは少ないといわれる。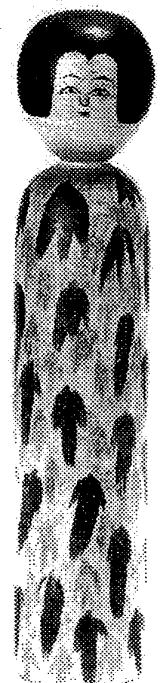 こけしに限らずあらゆる局面で、総じて現代人はどうも「良い」顔が書けなくなってきている傾向にあり、理由としてはいろいろ取りざたされるが、間接的には社会が近代化したこと、直接的には、誤った西洋史前主義的描写の学習、マンガアニメ的表現の影響などがあげられる。このような諸々の表情・目玉の善し悪しはどのような点で決まってくるのだろうか。また近現代の絵、もしくはマンガアニメのそれと比べどのような違いがあるのだろうか。表情の中でもとりわけ重要な「目玉」に話をしぼってそれらのことを少し考えてみたいと思う。
こけしに限らずあらゆる局面で、総じて現代人はどうも「良い」顔が書けなくなってきている傾向にあり、理由としてはいろいろ取りざたされるが、間接的には社会が近代化したこと、直接的には、誤った西洋史前主義的描写の学習、マンガアニメ的表現の影響などがあげられる。このような諸々の表情・目玉の善し悪しはどのような点で決まってくるのだろうか。また近現代の絵、もしくはマンガアニメのそれと比べどのような違いがあるのだろうか。表情の中でもとりわけ重要な「目玉」に話をしぼってそれらのことを少し考えてみたいと思う。
 その場合の登場人物の身ぶりは形式的、図式的で、一種の記号のようなところがあり、自然な身体の動き、動勢からは程遠いものが大半であったし、そこからはみだすものは稚拙なものばかりだった。それがチマブエ、ジョット以来生きた人間、現実の動き、表情というものが導入されるようになっていく。静止的な規範は後退し、画面構造として絵を背後から支えていくようになり、描かれる人物達はよりドラマチックに、よりリアルに描きわけられ、見る側に臨場感を誘う努力がほどこされはじめる。
その場合の登場人物の身ぶりは形式的、図式的で、一種の記号のようなところがあり、自然な身体の動き、動勢からは程遠いものが大半であったし、そこからはみだすものは稚拙なものばかりだった。それがチマブエ、ジョット以来生きた人間、現実の動き、表情というものが導入されるようになっていく。静止的な規範は後退し、画面構造として絵を背後から支えていくようになり、描かれる人物達はよりドラマチックに、よりリアルに描きわけられ、見る側に臨場感を誘う努力がほどこされはじめる。
 目玉や表情というのは実際のところよく動く。感情の動き、興味の変化に応じてそのニュアンスが刻々と変わっていく。その動きを静止した造形表現において志向する場合、先に述べた身体の動きにおける「気韻生動」と同様の問題が現れてくることがわかる。目玉や表情にもその気韻生動が生かされなければならず、したがって動き(変化)の一歩手前で寸止めされる必要がある。いくら怒りによって顔を崩した表情を造ったとしてもそれはそれだけのモノでしかなく、派手なわりに長続きするものではない。本当の怒り、恐さはやはり怒りの爆発の手前、爆発を予見させつつ、「ため」を持った「憤怒」の表情であり、目玉である。
目玉や表情というのは実際のところよく動く。感情の動き、興味の変化に応じてそのニュアンスが刻々と変わっていく。その動きを静止した造形表現において志向する場合、先に述べた身体の動きにおける「気韻生動」と同様の問題が現れてくることがわかる。目玉や表情にもその気韻生動が生かされなければならず、したがって動き(変化)の一歩手前で寸止めされる必要がある。いくら怒りによって顔を崩した表情を造ったとしてもそれはそれだけのモノでしかなく、派手なわりに長続きするものではない。本当の怒り、恐さはやはり怒りの爆発の手前、爆発を予見させつつ、「ため」を持った「憤怒」の表情であり、目玉である。






 それは暗に画中の聖職者が夢中で思いを巡らす神のことがら、形而上の世界へ向けられている。いわば神的偶像が視線を見る側に浴びせるのに対し、神との仲介者である聖職者の視線は文字どおり仲介となることで見る側の視線を上方へ誘う(同時にただ一方的に見られる対象物となった聖職の無防備な姿形が、生々しくそこに浮上してくるところがこの絵の肖像画としての面白いところでもある)。
それは暗に画中の聖職者が夢中で思いを巡らす神のことがら、形而上の世界へ向けられている。いわば神的偶像が視線を見る側に浴びせるのに対し、神との仲介者である聖職者の視線は文字どおり仲介となることで見る側の視線を上方へ誘う(同時にただ一方的に見られる対象物となった聖職の無防備な姿形が、生々しくそこに浮上してくるところがこの絵の肖像画としての面白いところでもある)。 
 このような構図、このような目玉の肖像画はレオナルド以後も肖像画の常套パターンとして、現在にいたるまで数多く描かれて来ているが、「立派な肖像画」、「良質の絵画」の域を出るものではない。そこでは「単体偶像表現」が持っていたものと同質の超越性、深遠性を「肖像画」というか「絵画芸術」に持ち込むことに失敗している、と言うよりもそういう次元そのものがその後の「美術」から忘却されてしまったのである。深遠な世界観を担ってきた中世的な、さらに広く言えば偶像表現的な顔・目玉-気韻生動のエッセンスは、レオナルドを一つの頂点として、あるいは分岐点として「美術」と袂をわけ、宗教や呪術というものに押し込められてしまったと言えるだろう。
このような構図、このような目玉の肖像画はレオナルド以後も肖像画の常套パターンとして、現在にいたるまで数多く描かれて来ているが、「立派な肖像画」、「良質の絵画」の域を出るものではない。そこでは「単体偶像表現」が持っていたものと同質の超越性、深遠性を「肖像画」というか「絵画芸術」に持ち込むことに失敗している、と言うよりもそういう次元そのものがその後の「美術」から忘却されてしまったのである。深遠な世界観を担ってきた中世的な、さらに広く言えば偶像表現的な顔・目玉-気韻生動のエッセンスは、レオナルドを一つの頂点として、あるいは分岐点として「美術」と袂をわけ、宗教や呪術というものに押し込められてしまったと言えるだろう。